Google Scholar では、Top publications として学術出版物における最近の論文の知名度や影響力をランキング化しています。
その中では、 Natureなど古くから知られる学術誌が含まれていますが、最近ではAI系の学会も多くなってきています。
今回の記事では、AMiner で Computer Science 分野に絞った Conference Rank が掲載されているので、それらの指標についてまとめていきます。
Conference Rank を決める 指標
以下の6つの指標がありますが、3つずつに分けて記事にしていきます!
- H5 Index
- Rising Index
- TK5 Index
- CCF Level
- Basic Research Creativity Index
- THU Level
ランキングのページは、こちらから
H5 Index
Google Scholar の top publications でも使われるこの指標。
まずは、h-index とは?という部分から説明していきます
辞書的に説明をすると、
「 h回以上引用された論文が h件ある ときの hの最大の数」です
例をあげると、
10本の論文を出している Aさん (被引用数 : 20,15,13,12,11,10, 5, 4, 3, 1)
5本の論文を出している Bさん (被引用数 : 100, 50, 30, 20, 10) とすると、
A さんの場合は、
6回以上引用された論文は 6件あるので、条件を満たすが、7回以上引用された論文は7件ないので、 h = 6
同様に、Bさんの場合は、
5回以上引用された論文が5件以上あるので、 h=5
といったように計算を行う
h-index のメリット
- 論文執筆数 や 被引用数 のどちらかが大きいだけでは、 h - index で高い値を出すことができないので、「量と質」の両立が求められる
h-index のデメリット
- h-index は 減ることのない値なので、研究者歴の長い人には有利に、若手や新興の学会には不利になってしまう
過去5年間に発表された論文に対して、h-index を計算したときの値
また、これによりh-index の減ることのない値という問題を緩和することができている
つまり、H5 Index が 301 の CVPR は、 過去5年間の論文で301回以上引用された論文が301件以上あることがわかりいかに影響力が大きいかがわかります!
Rising Index
同じ被引用数であっても、被引用数が増加している学会と被引用数が減少している学会では勢いが大きく変わってきます!
そこで、被引用数の増減を考慮することにより学会の盛り上がりを評価する指標として、Rising Index がとりあげられています。
過去5年間の被引用数 top100を対象に、被引用数が減少している論文の集合の中から、
H5 Index を適用させた値
例えば、 Rising Index = 91 の CVPRの場合は、
「直近5年間の被引用数top100の内、91件以上の論文の被引用数が減少していて、
かつ その中の H5 Index は 91 である。」
さらに、 H5 Indexが301であることを考えると、論文の被引用数が増加している論文が9件あるとも考えられますね。
といったように、指標をみることができます!
TK5 Index
H5 Index の指標では、量・質の両立も大事であるが、ある程度の絶対量が同等でないときに絶対量が多い学会ほど有利になりがちな指標でした。そこで、 TK5 Index では 上位の論文に対して学会の水準を定量的に反映することができるような指標となっています! 詳しい定義は以下の通りです。
過去5年間で 被引用数が高い top10の論文を対象に
それぞれの論文を引用したすべての論文に対して h-index を算出し、TK5値とすると、
10個の TK5値の中の中央値を TK5 Index とする。

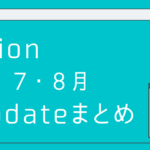

コメント